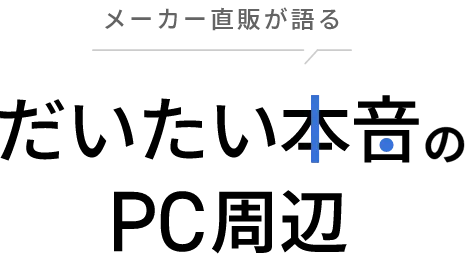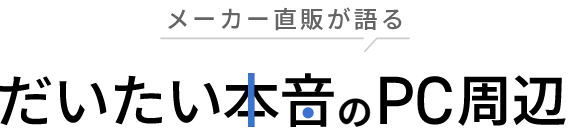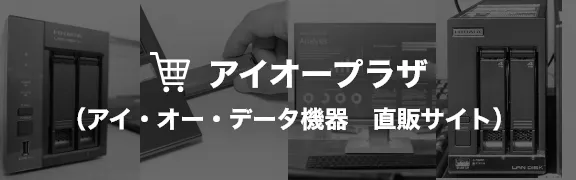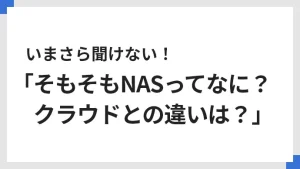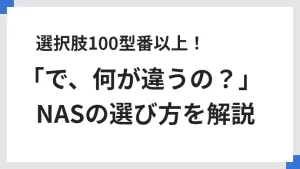こんにちは、PC周辺機器メーカー直販サイト「アイオープラザ」店員、NAS(ナス)の「なっさん」です!
今回は、
「ファイルサーバーとNASってどう違うの?」
という疑問を持つあなた、あるいはそれ以前に
「そもそもサーバーってなんなの?」
という疑問を持つあなたへ向け、敢えて技術的な話を全部横に置いてご説明します。
今回も“だいたい本音”でお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください!
ちなみに「NASってなに?」という方はまずこちらからどうぞ。
いまさら聞けない!「そもそもNASってなに? クラウドとの違いは?」
※本コンテンツは法人向けです。
大雑把な結論
まず最初に結論からいきます。
ただ、正直に申し上げるとこの結論はだいぶ大雑把です。
「いやいや、それじゃあ……」と思われてしまうかもしれませんが、とりあえず申し上げます。
Q:ファイルサーバーとNASってどう違うの?
A:同じと言えば同じで、違うと言えば違います。
「いやいや! それじゃあなにも解らないよ!」
と思われましたよね? すいません。
なんというかこの話、ひどく個人的な感覚で恐縮ですが、
「非常食と乾パンってどう違うの?」
「消毒薬とアルコールってどう違うの?」
みたいな質問に似てるのでは、と思うのです。
「まあ~、同じと言えば同じだし、違うと言えば違うよね~」
と言いたくなる気持ち、わずかでもお解りいただけますでしょうか?
もちろん、ここで「以上、終了!」とはなりませんのでご安心を。
じゃあ「一体どこが同じで、どこが違うのか?」というのをお話しさせてください。
ただ……その前にもうひとつ冒頭に挙げた疑問、
「そもそもサーバーってなんなの?」
にお答えします。
ファイルサーバー以前に、サーバーとは?
「そもそもサーバーってなんなの?」
これもひと言でお答えするのは難しいですが、とりあえず
「ビールサーバー」
をイメージしてください(ウォーターサーバーでも可)。
ビールを提供する器具、ですよね?
こんな風に「なにかを提供するもの」がサーバーです。
ただしIT業界で「サーバー」と言った場合、提供されるのはビールでも水でもなく「機能やサービス」ということになります。
例を出すと、提供されるサービスによって以下のような種類があります。
- Webサーバー
- DNSサーバー
- メールサーバー
- DBサーバー
- FTPサーバー


謎のアルファベットの羅列が出た! と思った方、ご安心を。
ここでご理解いただきたいのはそれぞれの機能ではありません。
例えばあなたがご覧になるインターネットのWebサイトも、誰かとやり取りするメールも、LINEやXなどのアプリも、全てこれらの「サーバー」が裏で動くことで、機能を実現しているということです。
その役割は様々ですが、概ねどんなサーバーにも共通するのは「多数のひとにサービスを提供する」ことが前提となっている点でしょう。
物理的な機器としての「サーバー」は、「コンピューター」です。
みなさんお使いの「PC(パソコン)」は「パーソナル・コンピューター」……つまり個人のためにあるものという前提ですが、サーバーはこの逆。
つまり「個人のためのもの”ではない”コンピューター」です。
これらの話から、改めて「そもそもサーバーってなんなの?」という疑問にお答えすると、
「多数のひとに、様々なサービスを提供するコンピューター」
ということになります。
そしてこのサーバーの種類のひとつが、
「ファイルサーバー」
です。


ファイルサーバーは「なにを」提供するサーバー?
では「ファイルサーバー」とは「なにを」提供するサーバーなのか?
誤解を恐れずに言うと、その名のとおり、あなたが仕事でお使いの文書、画像、動画などの「ファイル」です。
例えば社内の100人が同じファイルにアクセスし、閲覧・編集できる……そういう「みんなで使えるデータ領域」がファイルサーバーです。


「ん? それって……NASと同じじゃない?」
と思われた方、そのとおり。
それこそが冒頭で申し上げた「同じと言えば同じ」部分です。
「複数のひとがネットワークを介して共用できるデータ領域」という点は、ファイルサーバーもNASも変わりません。
と言うより、「NASはファイルサーバーの1種」と言ったほうが正確です。
「サーバーをファイルサーバーとして用いる」
「NASをファイルサーバーとして用いる」
どちらも成立する表現だと思います。より詳しく言うならこうなるでしょう。
「(機器としての)サーバーを、ファイルサーバー(という使い方)として用いる」
「(機器としての)NASを、ファイルサーバー(という使い方)として用いる」
要するに「ファイルサーバー」というのは、用途が強調された言葉です。
物理的な機器として「サーバー」と「NAS」は区別されますが、用途としてはどちらもファイルサーバーとして使えます。
だから冒頭で「同じと言えば同じで、違うと言えば違います」と答えました。
では、どうして「物理的な機器としては、サーバーとNASが区別される」のか?
私はそれを「成り立ち」の違いからご説明したいと思います。
サーバーとNASは「成り立ち」が違う
サーバーは上に書いたとおり「コンピューター」です。
これに対し、NASというのは”Network Attached Storage(ネットワークアタッチドストレージ)”という名が示すとおり「ストレージ」です。
当社の区分で言うと、ストレージに含まれる商品は「HDD(ハードディスク)」「SSD(エスエスディー)」「USBメモリ」等、要するに「データ記録媒体」です。
私たちがPC周辺機器メーカーとしてNASを作り始めたのは2000年代前半……「有線LAN接続HDD」として、でした。
これは、それまでUSBケーブルなどで接続するのが当たり前だったHDDというものを、”有線LANケーブル(ネットワークケーブル)で”接続できるようにした商品。
つまり「コンピューター」の流れではなく「PC周辺機器」の流れから、「みんなで使えるデータ領域」を提供し始めた、ということです。


「だからなに? 昔話なんてどうだっていいんだけど」
と思われたかもしれませんが、実はこの成り立ちを理解することが「サーバーとNASの違い」を理解する上で、とても重要だと私たちは考えています。
だから同じファイルサーバーでも
- コンピューターの流れを汲む「サーバー」は大規模環境向け
- 周辺機器の流れを汲む「NAS」は小規模環境向け
という違いが、今なお存在するのではと思うのです。
実のところNASも機器の内部構成(主要部品)は、「コンピューターと同じ」と言って差し支えありません。
それなのに「レンジが違う」だけでなく「名前が違う」のは、成り立ちが違うから……そんな風に捉えると、理解しやすいのではないでしょうか?
まとめ
以上の話からすると、NASというのは
「小規模環境向けのファイルサーバー」
と言えるでしょう。
ただし近年は当社NASのラインアップでも、上は「300人規模まで対応可能」な商品があり、必ずしも「小規模」だけのものではありません。
「NASのハイエンドモデル」と「ファイルサーバーのエントリーモデル」は、昔よりも近付いているのではないかと思います。
それでも、サーバーは「システムに組み込まれるもの」という性質が強く、「思い立ったらECで買ってすぐ導入」ということはほぼあり得ないでしょう。
逆に言うとNASは「思い立ったらECで買ってすぐ導入」が当たり前……ではないものの、やろうとすればできるものです。
当社もそのニーズにお応えすべく、多くのモデルで即納可能な在庫を持つようにしています。
↓当店売れ筋のミドルエンドNASを見てみる↓
8TB 推奨最大同時接続台数50台 法人向け2ドライブNAS HDL2-LV08
ですから基本的には「大規模なシステムに組み込む」ことが前提なら本格的なファイルサーバー、「中小規模的な使い方」が前提ならNASをお選びいただく、というのが良い選択ではないかと思います。
NASに合う規模や用途でお使いいただく場合は、多額の投資をせず「これで十分」と感じていただけるでしょう。
ちなみに、その意味で「NASに合う用途」のひとつには、
「ファイルサーバーのバックアップ」
という用途があります。
ファイルサーバーには高級なサーバーをお使いの場合でも、そのデータをバックアップする先ならNASで十分、ということが珍しくありません。
これについては次回、以下の記事で詳しくお話ししますので、ご興味のある方はぜひ併せてご覧ください。
NASを「ファイルサーバーのバックアップ」に使うメリットとは?
また、NASのラインアップを具体的に選びたい方には、以下をオススメします。
100型番以上ある機種の中から、「あなたに最適な1台」を選び出すための考え方をご説明し、チェックリストを掲載した記事です。
選択肢100型番以上!「で、何が違うの?」NASの選び方を解説
その他、「NASについての全般的なご相談」も広く受け付けております。
ここまで触れてきた内容の他、なにか導入の壁となるご懸念がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください!
投稿者プロフィール

-
PC周辺機器メーカー アイ・オー・データ機器の直販ECサイト「アイオープラザ」店員。
"難しい"PC周辺を"だいたい本音"で語り、"お客様が技術的な知識を学習せずに選べる店"を目指しています!
最近の投稿
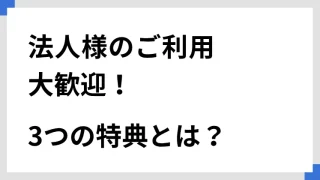 記事一覧2025年11月20日法人様のご利用大歓迎! 3つの特典とは?
記事一覧2025年11月20日法人様のご利用大歓迎! 3つの特典とは?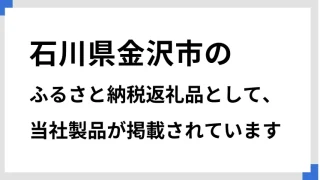 ふるさと納税2025年9月26日石川県金沢市のふるさと納税返礼品として、当社製品が掲載されています
ふるさと納税2025年9月26日石川県金沢市のふるさと納税返礼品として、当社製品が掲載されています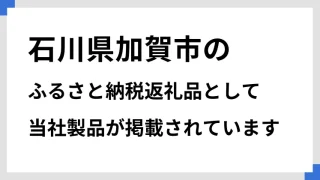 ふるさと納税2025年9月26日石川県加賀市のふるさと納税返礼品として、当社製品が掲載されています
ふるさと納税2025年9月26日石川県加賀市のふるさと納税返礼品として、当社製品が掲載されています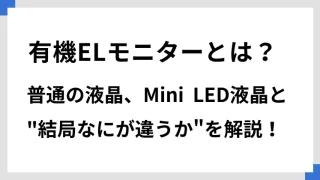 情報収集2025年8月29日有機ELモニターとは? 普通の液晶、Mini LED液晶と”結局なにが違うか”を解説!
情報収集2025年8月29日有機ELモニターとは? 普通の液晶、Mini LED液晶と”結局なにが違うか”を解説!